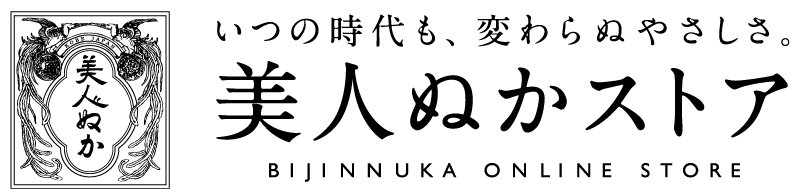お米はあまりにも身近すぎる。
お米って、いったいなんだろう?
私たちは、お米で何ができるんだろう?
お米は、何をしてくれるんだろう?
それは、たぶん、すてきな笑顔だったり、
くもりひとつない満足感。
つまるところ、幸せ。
お米の国で生きていく。
だからこそ、お米の力を、改めて。
お米の力を、もう一度。
知ってみたいと思うのです。

お米についてわかること

知っているようでよく知らない。
どこから来たの?
いつ来たの?
ずっと昔から身近な存在?
シンプルだけど、実はマルチ?
白くて小さい米粒のこと、探ってみました。
お米ってなに?

実は、たくさんの種類があるお米。その種類は全世界で1,000種類以上ともいわれています。大別すると、細長い粒のインディカ種(1)、丸くて短い粒のジャポニカ種(2)、そしてインディカ種とジャポニカ種の中間ぐらいの大きさの粒のジャバニカ種(3)の3種類。形状や性質で調理の仕方も炊いたり、炒めたり、蒸したり。世界各国で多彩な米料理があるのは、お米の種類が違うから。主食として、野菜として、とお米に対するとらえ方も国・地域によって違うのです。
さて、日本でおなじみのお米はジャポニカ種。全国各地で300種類以上の品種が育てられています。病気や天候に影響されにくい強くて、おいしいお米が開発されてきました。近頃は、冷えても固くならないお米や、タンパク質の摂取を制限されている人でも食べられるお米も誕生。
「海外に行くと、白い米粒が懐かしくなる」「おいしいお米を食べるのがいちばんの贅沢!」とはよく聞くセリフですが、それは日本人のDNAにお米が根付いている証拠。
そう、たぶん、私たちはお米でできているのです。
- インド、タイ、中国、またアメリカ大陸で生産されており、世界のお米の約80%を占めています。粘り気が少なく、パサパサした食感。
- 世界で生産される約20%がこの種類。日本や朝鮮半島、中国北部が主な生産地域。熱を加えると粘り気がでます。
- ジャワ型といわれ、東南アジアやイタリア、スペインで生産されています。あっさりした味わい。
お米とわたしたち

もしも、この国にお米がなかったら・・・。
歴史は変わっていたでしょう。日本に稲作が伝わったのは縄文時代末期から弥生時代。稲の化石やおにぎり形のお米の塊などが日本各地の遺跡で見つかっています。
稲作は、人々の暮らしに大きな変化をもたらしました。ひとつの土地に定住するようになり、ムラができ、リーダーが生まれ、ムラ同士が争い、国の誕生につながりました。邪馬台国の女王・卑弥呼もこのような状況で出てきたのでしょう。
稲作中心の社会になると、お米はお金の役割も持ちます。あるときは税金として。あるときは給料として。田んぼにまつわる法律も制定されました。そう、お米は食べること以外でも私たちに存在感を発揮するようになったのです。
もちろん、食生活でも、大きな存在でした。お米に魚介類や野菜のおかずという食習慣は、どうやら弥生時代にはできあがっていたもよう。
炊きたてのごはんに焼き魚、野菜のおつけもの、おみそ汁。ずっとずっと昔から、こんな理想的な食事を私たちは愛してやまないのです。
お米がちらり

いつも近くにあったお米は、文学や美術などにも取り上げられるほどでした。
日本に現存する最古の歌集「万葉集」では、お米や稲がたびたび登場(1)します。
長い黒髪が自慢だった平安時代の貴族の女性たちは、髪を米ぬかで洗い、とぎ汁で整えていたそう。日本文学史上最高傑作といわれる「源氏物語」にもお米で髪を整える描写があるので、当時はあたりまえの美容法だったのかもしれません。お米の美容法といえば、同じく平安時代に書かれた日本最古の医学書「医心方」には、お米を美白やシワ取りのバックに使ったという記述もあります。
また、江戸時代から大正時代の浮世絵美人画には、口に白い布をくわえているポーズがありますが、この白い布はぬか袋。ぬか袋は体や肌を洗うために、当時の女性たちの入浴タイムの必須アイテムだったのですね。恋のゆくえをお米や稲にたとえた歌、美しさのためにお米を活用する女の人の姿・・・。
お米はずっと私たちの生活や恋愛に関わってきたと知ると、はるか昔に生きていた人々も、グッと身近に感じられるから不思議です。
-
雲隠(くもがく)り 鳴くなる雁(かり)の 行きで居む 秋田の穂立(ほたち)繁(しげ)くし思ほゆ
作:大伴家持(おおとものやかもち)
訳:雲に隠れて鳴いている雁が降り立った秋の田の稲穂が繁っているように、(あのひとのことが)しきりに思われます。
あらき田の 鹿猪田(ししだ)の稲を 倉に上げて あなひねひねし 我(あ)が恋ふらくは
作:忌部黒麻呂(いむべのくろまろ)
訳:新しく開墾した、鹿や猪が荒らす田でとれた稲を、倉に納めましたが、長い年月がたち、お米が古くなるのと同じように私の恋も古くなってしまいました。
お米はえらい

とにかく、バランス抜群。あんなに小さい粒なのに、お米には栄養成分がギュッと凝縮されています。
その主な成分は炭水化物の一種であるデンプン。脳やからだを活発に働かせるエネルギー源になります。「ごはんは何も味付けをしてなくても、かめばかむほど甘くなる」のはデンプンが口のなかで、甘みのあるブドウ糖に変わっていくからなのです。ほかにも、タンパク質、鉄分、ビタミンB1、食物繊維などさまざまな栄養成分を含有。ごはん1杯で、からだに必要な栄養を取ることができるといわれています。
米穀店でお米を注文する際、「五分づき(1)で」「玄米で」と精米率をオーダーする人も増えている玄米。白ごはんに慣れているとぼそぼそした食感に戸惑いますが、ぬかや胚芽に含まれるビタミンやミネラルが白米より多いため、好んで食べる人も多いのです。
栄養たっぷり、おなかがすきにくい、太りにくい、消化吸収がよい…などなどお米をほめる言葉は次から次へ。マルチな才能を秘めているのです。
- 白米の精米率を10割として、何割精米したかを表す言葉。玄米→3分づき米→5分づき米→7分づき米→白米と精白度が高くなります。玄米のぼそぼそ感や炊飯に慣れていない人は、7分づき米からトライするのがおすすめです。
お米と暮らし

一年を通じてさまざまなおまつりや行事がある日本。それらの多くは、お米の豊作を願い、稲作の神様を祀る儀式といわれています。
新しい年を祝うお正月(1)、現代では桜の咲く時期のお楽しみになっているお花見(2)、九月中から下旬の満月の日限定の十五夜(3)などは日本に稲作があったからこその伝統行事です。夏に各地で行われる盆踊りは、先祖の霊を供養する行事と豊作を祈る行事が一緒になったという説も。青森のねぶた祭りや徳島の阿波踊りもそのひとつだそうです。またお相撲は五穀豊穣を祈る儀式が起源。四股を踏むのは田の神が田んぼから消えないことを祈る意味があったと考えられています。
おまつりや儀式は豊作を祈り、感謝するために行われる特別なものですが、人々の暮らしから生まれた文化風習もあります。「田植え歌」「米つき歌」などは農作業中に歌ったもの。みんなで土を耕したり、稲を植えながら歌ったのでしょう。またお食い初め(4)や枕飯(5)にもお米は重要な役割で登場します。
一年の折々に、そして人生の節目に、お米は私たちに深く関わっているのですね。
- 神様を迎えるために家中に飾るしめ飾りやしめなわ、神様の力が宿ると考えられていた鏡に見立てた丸いお餅=鏡もちなどのお正月のしきたりはお米づくりに関係しています。
- 本格的な農作業が始まる前に山から降りてきた田の神をもてなし、豊作を祈るために行われていました。
- 稲穂に見立てたススキを飾り、月見だんごを食べながら満月を眺めます。稲の収穫を感謝するために始まったといわれます。
- 生後100日目頃に、子どもが一生食べものに困らないことを祈ってごはんを食べさせるまねをします。
- 亡くなった人の枕もとに供えるごはん。愛用のお茶碗にごはんを高く盛り、中央に箸を立てます。
守って、守られて。コウノトリと生きる
兵庫県豊岡市コウノトリ育む農法
日本にはお米を作っている地域がたくさんあります。なかでも注目を集めているのが兵庫県豊岡市。日本の空から消えたコウノトリを復活させるためのプロジェクトのひとつとして生まれたお米づくり「コウノトリ育む農法」は、取り組みから約20年。年々、豊かな実りを見せるようになっています。
西洋では赤ちゃんを運んでくる鳥として知られるコウノトリは、日本でも幸せを運ぶ鳥として親しまれてきました。漢字で「幸の鳥」と書いたという説も。田んぼや畑に生息する様々な生きものをえさにしているので、里山が活動エリア。自然が多く残っていた昔の江戸には数多く暮らしていたともいわれています。
その姿が鶴に似ているため、豊岡では鶴と呼ばれていたコウノトリですが、主なえさ場となる田んぼの稲を踏むのではといった憶測、森林の伐採や乱獲、農業の近代化による農薬散布・化学肥料の使用など様々な要因が重なり、1971年(昭和46年)に豊岡で生息していた野生コウノトリが絶滅。日本の空からコウノトリは姿を消すことになりました。
もう一度、豊岡の大空にコウノトリを。そんな願いから動き出したのがコウノトリと共生するまちづくり。絶滅したコウノトリを復活させるには、緑豊かな山、清らかな水が流れる川、えさとなる生きものがたくさんいる田んぼなどが欠かせません。コウノトリと人がともに暮らせる農業として農薬・化学肥料にできるだけ頼らないお米づくりは始まりました。豊岡に生きるコウノトリも約306羽に増えました。
ちょうど食材への関心も高まってきた時期ゆえ、安全なお米と生きものを同時に育む農法で育てた「コウノトリ育むお米」も脚光を浴びることに。コウノトリ育む農法を行う米農家の北村真二さんも遠方からの注文が多い、一度買った人は繰り返し買い求めると話します。
ドジョウやフナ、カエルにバッタなどが生きる田んぽ、その生きものを求め里山にやってくるコウノトリ、その田んぼで作られたお米を食べる私たち人間。互いを守り、守られながら、生きていく豊かな命のめぐりがここにはあるのです。